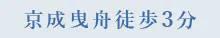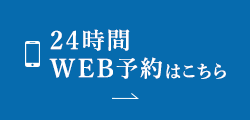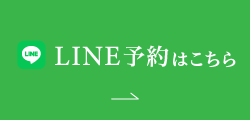尿の泡立ちが気になる方へ
 尿の泡立ちに気付き、タンパク尿を疑って泌尿器科を受診する方もいらっしゃいます。実際、慢性腎臓病などの疾患では、尿中のタンパク質の増加によって尿が泡立つことがあります。しかし、尿の泡立ちの原因は多岐にわたり、膀胱炎などの尿路感染症が原因で尿が泡立つことがあります。当院では、泌尿器専門医の院長が丁寧な診療を行っております。お気軽にご相談ください。
尿の泡立ちに気付き、タンパク尿を疑って泌尿器科を受診する方もいらっしゃいます。実際、慢性腎臓病などの疾患では、尿中のタンパク質の増加によって尿が泡立つことがあります。しかし、尿の泡立ちの原因は多岐にわたり、膀胱炎などの尿路感染症が原因で尿が泡立つことがあります。当院では、泌尿器専門医の院長が丁寧な診療を行っております。お気軽にご相談ください。
尿が泡立つメカニズム
最近は洋式便器が普及し、男性も座って排尿する機会が増えたため、尿の泡立ちに気づく機会が減っています。いつもは気付きにくい尿の泡立ちも、公衆トイレなどで排尿した際に気付く方もいらっしゃいます。
石鹸を例に挙げると、泡立ちの要因は、石鹸に含まれる界面活性剤の働きにあります。水もペットボトルなどに入れて振ると一時的に泡立ちますが、すぐに消えます。これは、水の表面張力により泡が瞬時に小さくまとまるためです。
一方、水に石鹸を加えると、石鹸の界面活性剤が水の表面張力を弱め、泡が消えにくくなります。つまり、尿の泡立ちも、尿中の不純物が界面活性剤のように働くことで起こると考えられます。
尿が泡立つ原因
尿の泡立ちの主な原因は、尿タンパクです。タンパク質は石鹸の界面活性剤と同様の性質を持つため、尿中のタンパク質濃度が上昇すると尿が泡立ちやすくなります。
尿タンパクの増加は、糖尿病性腎症・ネフローゼ症候群・腎炎などの慢性腎臓病によって引き起こされることがあります。他にも、脱水による尿の濃縮によって泡立ちが見られる場合があります。また、黄疸(おうだん)によるビリルビン尿、膀胱炎などの尿路感染症による尿の混濁、子宮がんの放射線治療後や大腸憩室炎によって起こる膀胱腸瘻(ぼうこうちょうろう)なども、腸管内のビリルビンやガスが尿に混ざり、泡立ちが増す場合があります。
このような尿の泡立ちは心配ありません
前述のように、尿は脱水状態が原因で泡立つこともあります。実際に尿の泡立ちで受診された患者様の中で、脱水による一時的な尿の濃縮が原因だったケースがよくあります。これは病気ではなく生理的な現象です。
腎臓は優れたろ過機能を持ち、体内の水分量を敏感に感知し、多量の水分がある場合は尿量を増やし、不足している場合は尿量を減らします。脱水状態になっている場合は、体内の水分量を保つために尿量を少なくします。これにより、肝臓で生み出される胆汁の代謝産物である尿中のウロビリノーゲンの濃度が上昇します。これが尿の泡立ちの原因です。
寝ている間は水分補給することがないため、起床時は軽度の脱水状態であることが多く、尿が泡立つ場合があります。また、ウロビリノーゲンが酸化するとウロビリンという黄色い物質に変わるため、起床時は色が濃い尿が出ることがあります。
尿の泡立ちが起こる疾患
尿タンパク(ネフローゼ症候群・腎炎など)
尿タンパクは、腎臓のろ過機能が低下し、尿中のタンパク質濃度が上がった状態を指します。腎臓は、血液をろ過して過剰な水分や老廃物を尿として体外に出す役割を担っています。これは腎臓内に100万個存在するとされる糸球体という微小なろ過装置によって行われます。
健康な状態では、タンパク質は糸球体のフィルターを通ることがないため、尿中のタンパク質濃度は少ないです。しかし、ネフローゼ症候群や腎炎、高血圧性腎症(腎硬化症)、糖尿病性腎症などの病気が起こると、糸球体のフィルターの網目が損傷し、尿中にタンパク質が流出してタンパク質濃度が上がります。尿中のタンパク質濃度が上がると、尿の泡立ちに繋がります。
糖尿病
糖尿病が進行すると、尿中にブドウ糖が排出されることがあります。例えば、尿糖の検査結果が(++++)の場合、ブドウ糖濃度は1000mg/dLであることを示します。これは、1Lの尿中に大さじ1杯分のブドウ糖が溶け込んでいる状態に相当します。ブドウ糖そのものは界面活性作用を持たないため、尿の泡立ちがブドウ糖濃度に直接起因するかどうかは、現在のところ結論付けられていません。しかし、糖尿病が進行し、糖尿病性腎症を併発するとタンパク尿が見られ、それに伴い尿が泡立つことがあります。
したがって、尿の泡立ちが見られた際には、糖尿病の可能性を念頭に置くことが大切です。検査で尿糖が陽性と判定された場合、糖尿病の疑いが強いと考えられます。
尿路感染症
尿路感染症は、尿の通路である腎盂や膀胱などの粘膜で細菌感染が起こった状態です。主な病気としては、膀胱炎や急性腎盂腎炎などが挙げられます。これらの病気が起こると尿中に白血球が混入し、膿尿となって尿が濁ります。また、細菌感染によって尿中の尿素窒素が分解されるとアンモニアが作り出されるため、尿が強い臭いを発したり、尿がアルカリ性に傾いたりします。さらに、粘膜で細菌感染が起こるとタンパク質が滲出し、尿が泡立つ場合があります。
黄疸(おうだん)
黄疸は、肝機能の低下によって皮膚や白目などが黄色く変色する状態です。代表的な原因は、溶血性貧血や肝疾患などです。肝機能が低下して黄疸が起こると、ビリルビンという肝臓で生成される胆汁成分が尿中に混ざります。ビリルビンは茶褐色~緑色を呈するため、尿の色もオレンジ色~茶褐色へと変化します。このビリルビンは界面活性作用を持つため、尿が泡立つことがあります。
膀胱腸瘻(ぼうこうちょうろう)
膀胱腸瘻は、大腸と膀胱の間に穴が形成され、両者が繋がる状態です。大腸憩室炎が起こると腹痛などの症状が現れますが、この炎症が重症化・長期化すると、隣接する膀胱壁に炎症が波及し、膀胱腸瘻を引き起こすことがあります。また、子宮がん治療などで放射線療法を受けた場合も、その後の合併症として膀胱腸瘻を発症する場合があります。
膀胱腸瘻を発症すると、ウロビリノーゲンやビリルビンなどの腸の内容物が膀胱内に混ざったり、腸管内のガスが尿中に混入したりするため、尿が泡立ちます。
正常な泡立ち(尿が濃い)とは
尿の泡立ちには様々な原因が考えられますが、一般的なものは脱水による尿の濃縮です。これは病気ではなく、生理的な現象と言えます。
脱水状態になると、尿中に排出されるウロビリノーゲンという物質の濃度が上昇します。ウロビリノーゲンは、肝臓で生成された胆汁(ビリルビン)が代謝されることで作られる物質であり、基本的に尿中に含まれています。尿検査では、このウロビリノーゲン濃度を迅速に調べることが可能で、正常値は(±)とされています。
ウロビリノーゲンは界面活性作用を持つため、尿中の濃度が上がると尿が泡立ちやすくなります。起床時の尿や運動後に汗をかいた後の尿が泡立ちやすいのは、睡眠中や運動によって体が脱水状態になるためです。また、尿が濃縮されると、アンモニア臭が強くなります。