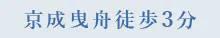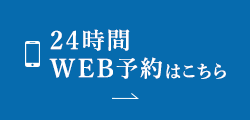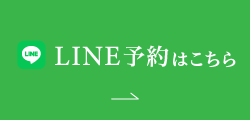尿の濁りについて

正常な尿の色は透明で黄色っぽい色ですが、尿が白く濁る(尿白濁)場合があります。尿中の塩類が結晶化すること、血尿、尿路の細菌感染が主な原因で、女性ではおりものの混入によって尿白濁が起こる場合もあります。尿白濁の原因について、以下で詳しく説明します。
尿が濁る主な原因
食事
シュウ酸が豊富なバナナやホウレンソウ、ココア、タンパク質や動物性脂肪などを摂り過ぎると、尿中に小さな結晶ができ、尿が濁る場合があります。この場合、尿路結石を引き起こす可能性があり、食生活などの生活習慣を改善することが必要です。
女性ならではの原因
生理中の経血やおりものが尿に混入することで、尿が濁る場合があります。なお、女性は膀胱炎を発症しやすく、慢性膀胱炎の場合、尿の濁りのみが生じ、他の症状は違和感くらいのこともあります。排尿痛、性器やその周りのかゆみなどがなくても、尿の白濁が長引いている場合は、なるべく早めに当院までご相談ください。
性行為によって起こる性感染症
クラミジアや淋菌といった性感染症は、炎症によって尿の濁りが起こる場合があります。これらの性感染症は、症状がほとんど現れないまま進行することが多く、男女いずれも将来的に不妊が起こる恐れがあります。近年、梅毒やクラミジアの感染者数が増えているため、十分に注意してください。性感染症は、男女で症状の現れ方に大きな違いがある場合があります。淋菌は、男性では激しい症状が現れやすいですが、女性の場合、ほとんどが無症状であるか、軽度の症状しか現れません。症状の有無にかかわらず、パートナーも検査を受けることが重要で、治ってからも再感染しないように注意しましょう。
尿の濁りを引き起こす代表的な疾患
尿の濁りは、多岐にわたる泌尿器系の疾患によって引き起こされます。尿管や膀胱の結石、性感染症、腎盂腎炎・膀胱炎・尿道炎などの尿路感染症、腎結核、進行した前立腺がん、膀胱がん、腎臓がんなどがその代表例です。濁りが著しい場合は、尿路感染症の悪化により膿が尿に混入している場合があります。
腎臓結石・尿管結石
尿中のカルシウムやシュウ酸といった成分が結晶化し、狭い尿管に詰まることで、尿の濁りだけでなく、排尿障害や血尿が現れる場合があります。尿管に結石が詰まり尿の流れが滞ると、背中・脇腹・腰などに突如として強い痛みが現れ、吐き気・嘔吐、冷や汗などが起こる場合もあります。
腎盂腎炎
細菌感染による炎症が腎臓まで広がると、尿中に白血球が混入し、尿が濁ります。吐き気・嘔吐、腰や背中の痛み、高熱、血尿などの症状が起こる場合もあります。特に、膀胱炎が何度も起こると腎臓へ感染が広がりやすくなるため、膀胱炎を繰り返しやすい女性に発症しやすい傾向があります。
急性膀胱炎
排尿の終わり際のツンとした激しい痛みや頻尿が起こりやすいですが、血尿や尿の濁りもよく見られる症状です。尿道から侵入した病原体が膀胱に侵入し、免疫力が落ちていると感染リスクが高まります。膀胱炎には様々な種類があり、治療法に違いがあります。間質性膀胱炎では、尿が膀胱に溜まると痛みが起こり、排尿によって症状が軽減されます。
尿道炎
尿道の長い男性に多く見られる病気で、尿道に侵入した細菌が粘膜に感染して炎症が生じます。クラミジアや淋菌などの性行為によって感染する菌が原因となります。クラミジアは男女いずれも症状が少なく、淋菌も女性が感染した場合は自覚症状が乏しいです。しかし、いずれも男女ともに将来の不妊をもたらす恐れがあります。陽性と診断された場合は、症状の有無を問わずパートナーも必ず検査を受けることが重要です。
淋菌感染症
淋菌の感染によって起こる性感染症です。男性は排尿の初めに激しい痛みが起こり、尿に膿が混入して濁ることが多く見られます。女性は感染してもおりものの変化や軽いかゆみくらいの症状が生じるのみで、症状が起こらないこともよくあります。妊娠中に感染すると、母子感染によって赤ちゃんが失明するリスクもあります。
性器クラミジア感染症
クラミジアの感染によって起こる性感染症です。男性が感染した場合、微量の膿が尿に混ざって濁る、排尿の初めにしみるような軽い痛みが起こりますが、症状が現れない場合もあります。女性は感染しても無症状のことが多いです。昨今、感染者数が増えており、妊娠中に感染すると、母子感染で赤ちゃんが結膜炎や重度の肺炎を発症する場合があります。
前立腺炎
男性特有の生殖器官である前立腺で炎症が生じる疾患です。20~30代の若年層の発症が目立ちます。排尿の初めに軽い痛みが起こり、頻尿などをきたす場合もあります。悪化すると激しい排尿痛が起こり、高熱や下腹部の痛み、尿の濁りなどが生じる場合があります。前立腺肥大症に進行する場合もあるため、完治するまで治療を続けることが大切です。
腎結核
血液に結核菌が混入し、腎臓で感染が起こる疾患です。発症初期は尿が濁りますが、その他の症状は起こりません。進行すると腎臓内で膿が増加して尿の濁りが増し、下腹部の強い痛みや高熱が生じます。
腎臓がん・膀胱がん・前立腺がん
発症初期は自覚症状が乏しいですが、目視できないくらい少量の血液が尿に混入し、健康診断などの尿検査で尿潜血陽性となる場合があります。このような少量の血液によって軽い尿の濁りが起こる場合もあります。尿潜血陽性となった、もしくは軽い尿の濁りがある場合は、すぐに当院までご相談ください。なお、前立腺がんについては、腫瘍マーカーのPSAが早期発見に有効です。
尿の濁りを防ぐために
尿の白濁は、様々な泌尿器疾患によって引き起こされる症状であり、なかにはがんのような重篤な疾患が原因となることもあります。また、近年感染者数が増え続けている性感染症も、尿の白濁を引き起こす原因の1つです。性感染症は、感染しても自覚症状が現れないことが少なくありません。そのため、ご自身に尿の白濁が見られた場合は、症状の有無を問わずパートナーも検査を受けることが大切です。
食生活の改善

尿の濁りから尿路結石が判明することがあります。ココアやホウレンソウにはシュウ酸が豊富に含まれるため、これらの摂取を減らすことで結石が生じづらくなります。一方で、柑橘類や緑黄色野菜は意識して摂取しましょう。
性交渉時のコンドームの使用
性交渉の最初から最後までコンドームを適切に使用することで、避妊はもちろん、性感染症を防ぐことにも繋がります。なお、コンドームを使用しても発症を防止できない性感染症も存在します。当院では、性感染症の予防や避妊についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
このような尿の濁りは心配ありません
シュウ酸の摂り過ぎ
シュウ酸はえぐみや苦みなどアクのような味を感じる成分で、食品に少量含まれていると特有の風味が出ます。シュウ酸が豊富に含まれる食品としては、バナナ、タケノコ、ホウレンソウ、チョコレート、コーヒー、紅茶、緑茶などが挙げられます。
シュウ酸を摂り過ぎると尿中のシュウ酸が増えて尿が濁りますが、一時的なもので頻発しなければ心配はいりません。なお、日頃からシュウ酸を過剰摂取している場合、尿中のカルシウムと結合して尿路結石が生じやすくなるため、気を付けましょう。
動物性タンパク質の摂り過ぎ
動物性タンパク質を摂り過ぎると体内のシュウ酸が増加し、尿が濁る場合があります。アミノ酸やプロテインなどのタンパク質をサプリメントで過剰摂取すると、尿の濁りだけでなく腎臓へのダメージが増加しますので、用法容量を守って摂取しましょう。
おりものの混入(女性の場合)
女性は、おりものが混入することで尿が濁って見える場合があります。一時的な濁りの場合や別の症状が無い場合は、大きな心配はいりません。
ただし、おりものは健康状態を表す指標となるため、おりものの状態をしっかりと確認することが大切です。おりものの色がいつもと違う、量が変わった、悪臭がするなどの異変があれば、一度当院までご相談ください。