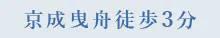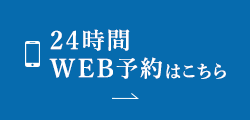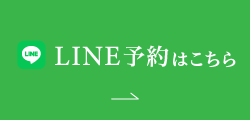むくみとは
 むくみは、皮膚の下に過剰な水分が蓄積した状態です。
むくみは、皮膚の下に過剰な水分が蓄積した状態です。
人体の6割は水分で成り立っており、その内訳は細胞内液が4割、細胞外液が2割です。むくみは、この細胞外液のバランスが崩れることで発生します。
基本的に、細胞外液は細胞間にある組織間液が15%、血液(リンパ液や血漿)が5%の割合で構成されています。これらの水分は毛細血管を経由して循環し、細胞への栄養供給や老廃物除去を行っています。健康な状態では、これらの水分の割合は常に一定に保たれています。しかし、何らかの原因でこのバランスが乱れ、組織と細胞の間に過剰な水分が貯留すると、むくみが生じます。
むくみの原因
むくみは、毛細血管から細胞間へ流出する水分が過剰になることやリンパ管や毛細血管への水分吸収が減少することで発生します。
これらの現象は、主に血液循環の悪化によって引き起こされます。
特に下肢は心臓より低い位置にあるため、重力の働きで血液が心臓に戻りにくくなります。通常は、静脈の逆流防止弁の働きとふくらはぎの筋ポンプ作用によって血液が心臓へと送り返されます。しかし、長時間同じ姿勢で立ち続けたり、座り続けたりすると、ふくらはぎの筋ポンプ作用が十分に機能せず、下肢の血液循環が悪化します。また、ガードルなどの締め付けの強い下着を着用することも、血液循環を阻害し、むくみの原因となることがあります。食事においては、過剰な塩分摂取がむくみを引き起こします。人体には、塩分濃度を一定に維持する機能が備わっているため、塩分を過剰に摂取すると、体は水分を溜め込んで塩分濃度を薄めようとします。
むくみを引き起こす疾患
むくみは、疾患の兆候となることがあります。顕著なむくみが見られる場合には、腎臓、心臓、肝臓などの疾患が疑われます。これらの疾患によるむくみは、指で圧迫すると跡が残りやすく、全身に現れます。
腎機能障害:腎臓病、腎不全
腎臓は、血中の老廃物をろ過し、尿として体外に出す重要な役割を担っています。腎機能が低下すると、老廃物を含んだ水分の排出に支障をきたし、体内に水分が蓄積することでむくみが生じます。
心不全
心臓が血液を効率良く送り出すことができなくなる状態で、全身の血液循環が滞り、むくみが生じることがあります。
肝硬変
肝臓全体が硬化することで、肝臓でのアルブミンなどのタンパク質合成能力が低下します。アルブミンは血管内の水分を維持する役割を担っているため、血中のアルブミン濃度が下がると、水分が血管から間質に流出し、全身にむくみが生じます。
栄養失調
栄養失調によってタンパク質が欠乏すると、血液中のアルブミンが減少し、全身にむくみが生じます。
下肢静脈瘤
女性によく見られる疾患で、下肢の静脈が拡張し、血流が停滞することで足がむくみます。重症化すると、皮膚表面に静脈が瘤状に浮き出ます。
リンパ浮腫
手術によるリンパ節の切除などによってリンパ液の流れが停滞することで、患部にむくみが生じます。
むくみの診断
ほとんどのケースでは、視診および触診によって四肢の太さに左右差がないか、皮膚の硬度や色調に変化がないかなどを確かめることで診断できます。リンパ液が蓄積して皮膚が肥厚すると、皮膚を引っ張った際にしわができにくくなったり、皮膚をつまみにくくなったりする変化が認められます。
※症状に応じて提携先の医療機関とも連携しながら適切な診断を下します。
むくみは当院までご相談ください
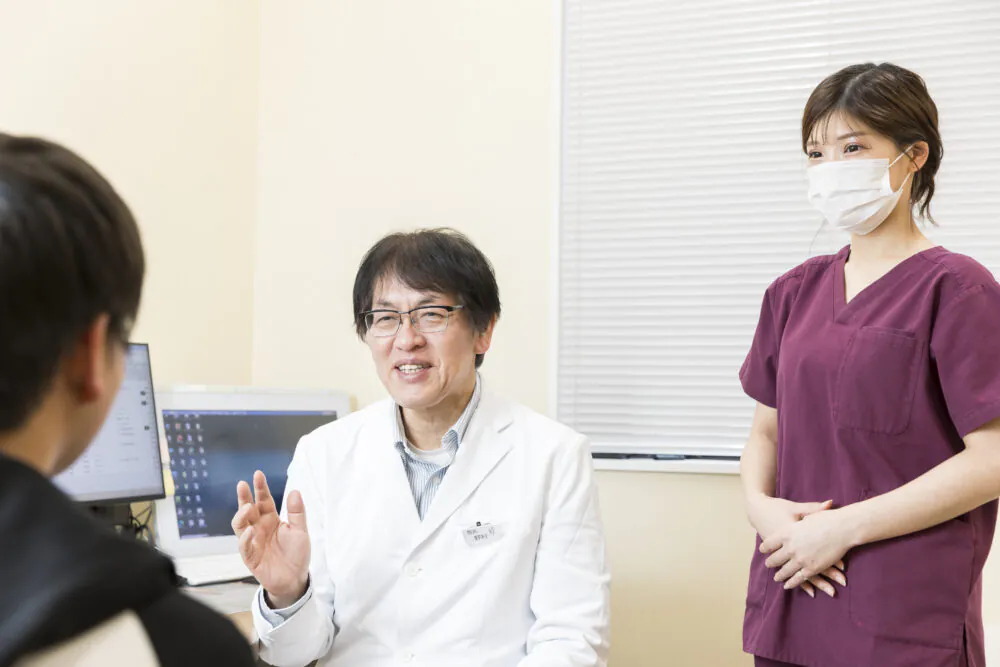 むくみは泌尿器の疾患によって生じることがあります。腎不全やネフローゼ症候群、腎炎、尿路閉塞などの疾患により体内の水分やナトリウムの調整がうまくいかなくなり、浮腫が起こることがあります。当院では泌尿器専門医が丁寧な診療を行っております。浮腫みにお悩みでしたら、当院までお気軽にご相談ください。
むくみは泌尿器の疾患によって生じることがあります。腎不全やネフローゼ症候群、腎炎、尿路閉塞などの疾患により体内の水分やナトリウムの調整がうまくいかなくなり、浮腫が起こることがあります。当院では泌尿器専門医が丁寧な診療を行っております。浮腫みにお悩みでしたら、当院までお気軽にご相談ください。