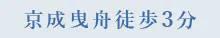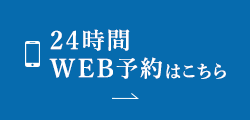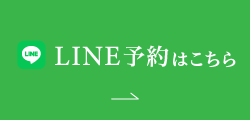残尿感について
 残尿感は、排尿後も膀胱に尿が残っている感覚があり、スッキリしない状態です。実際に膀胱内に尿がある場合と無い場合があり、尿がある場合は尿路感染症のリスクが高まります。残尿感は様々な泌尿器疾患で起こります。
残尿感は、排尿後も膀胱に尿が残っている感覚があり、スッキリしない状態です。実際に膀胱内に尿がある場合と無い場合があり、尿がある場合は尿路感染症のリスクが高まります。残尿感は様々な泌尿器疾患で起こります。
早めに治療が必要な病気が原因となっている場合もあるため、お悩みの方は一度当院までご相談ください。
残尿感が生じる主な疾患
膀胱炎
膀胱炎は残尿感や排尿痛、頻尿などが生じます。細菌感染が原因となる急性膀胱炎は発症率が高く、抗生物質を使って治療しますが、昨今は耐性菌も増えています。そのため、検査結果をもとに効果的な抗生物質を選定し、治療することが大切です。また、トイレを我慢するなどの生活習慣によって膀胱炎が起こる場合もあるため、何度も再発する場合は生活習慣を改善することも大切です。
細菌感染以外の原因によって起こる膀胱炎もあり、タイプによって治療が異なるため、まずは原因特定のために当院までご相談ください。
神経因性膀胱
脊髄や脳の外傷・病気などが原因で、脳から尿道や膀胱に適切に信号が送られなくなり、排尿障害が発生する病気です。実際に膀胱内に尿が残った残尿感が起こりやすく、原因となる外傷や病気を治療することで、症状が軽減します。また、神経の働きや排尿機能を改善するお薬を用いることで、症状が改善される場合もあります。実際に膀胱内に尿が残ることで起こる残尿感が改善されない場合は、腎機能障害や炎症性疾患を防ぐために、自己導尿を実施することもあります。
骨盤臓器脱
骨盤の中の尿道、膀胱、子宮といった臓器は、骨盤底筋群という筋肉によって適切な位置に保持されています。しかし、加齢、妊娠、出産などの影響で骨盤底筋群が弛緩すると、これらの臓器を支えきれなくなり、本来の位置よりも下がる(下垂)場合があります。軽度の下垂であれば、自宅で手軽に行える骨盤底筋群のトレーニングによって、症状の改善や状態の維持が期待できます。しかし、症状が進行している場合は手術が検討されることがあります。
心因性頻尿
薬物療法による対症療法に加え、水分摂取のタイミングや量などの生活習慣を改善し、骨盤底筋群のトレーニングなどに取り組むことで、症状の改善を目指します。
前立腺肥大症
前立腺は男性特有の生殖器官で、尿道を囲むように位置し、膀胱のすぐ近くに存在します。年齢を重ねると前立腺が肥大しやすくなり、その結果、周辺の尿道や膀胱を圧迫し、頻尿や残尿感などが発生します。治療としては、主に薬物療法が選択されますが、症状の改善効果が薄い場合や、症状が重い場合、または合併症が起こっている場合は、手術を行うことがあります。
過活動膀胱
膀胱にごく少量の尿しか溜まっていないのに、強い尿意を感じる状態です。加齢、膀胱の知覚過敏、自律神経の乱れなどによって起こります。主な症状としては、残尿感のほか、頻尿、突然強い尿意に襲われる尿意切迫感、尿意切迫感によりトイレに間に合わず失禁してしまう切迫性尿失禁などが挙げられます。治療としては、薬物療法での症状改善と並行して、膀胱訓練や生活習慣の改善などを行い、根本的な改善を目指します。また、原因となる病気がある場合は、その病気に対する適切な治療を行うことが大切です。
尿路結石
尿に含まれるシュウ酸やカルシウムなどが結晶化し、それが固形物となった結石が、腎臓から細い尿管に移動して詰まることで、腰や背中の強い痛み、残尿感、血尿などの症状が現れます。結石がある場所により、腎臓結石・尿管結石・膀胱結石・尿道結石と分類されます。放置すると、腎臓に深刻なダメージが蓄積し、重篤な腎機能障害に繋がる恐れがあります。そのため、気になる症状が現れた場合は、速やかに当院までご相談ください。
膀胱がん
膀胱は尿を一時的に蓄え、脳からの信号によって収縮し、尿を排出する役割があります。腎盂・尿管・膀胱・尿道の内側は尿路上皮と呼ばれる組織で覆われており、膀胱がんはこの尿路上皮に生じます。膀胱がんの特徴として、血尿・排尿痛・頻尿などが比較的早期に起こりやすく、特に鮮やかな赤い血尿が見られるのが特徴です。血尿があっても痛みを伴わないことが多いため、早期発見しやすいがんです。
残尿感が続く
 排尿後に尿が完全に出ていない感覚が続き、尿が残っているような不快感がある状態を「残尿感」と呼びます。
排尿後に尿が完全に出ていない感覚が続き、尿が残っているような不快感がある状態を「残尿感」と呼びます。
前立腺肥大症が主な原因です。前立腺が膀胱の出口を圧迫することで、尿の排出が妨げられて残尿感が現れます。また、尿道狭窄や尿路感染症、膀胱炎などの泌尿器疾患、さらに、脊髄損傷や神経因性膀胱などの神経障害によって残尿感が現れる場合もあります。
当院では、泌尿器専門医が丁寧な診療を行っております。気になる残尿感がありましたらお気軽にご相談ください。