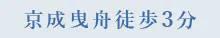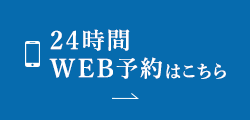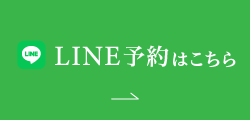頻尿と過活動膀胱の違い
頻尿と過活動膀胱は、どちらも排尿回数が増加するという共通の症状がありますが、原因や症状の特徴は異なります。
頻尿
頻尿は、排尿回数がいつもより多くなっている状態で具体的には1日6回以上、もしくは夜間に2回以上排尿する場合を指します。必ずしも尿量の増加を伴うとは限りません。
頻尿の原因
- 尿路感染症や膀胱炎などの炎症
- 膀胱結石
- 前立腺肥大症
- 尿路感染症
- 腎機能低下
- 糖尿病などの代謝異常
- 水分摂取量の増加
- 妊娠や更年期などのホルモンバランスの変化
過活動膀胱
過活動膀胱は、膀胱の筋肉が自分の意思とは関係なく収縮することで、尿意を催す状態です。急激な尿意で排尿のコントロールが困難になり、我慢できずに漏らしてしまう切迫性尿失禁を伴うこともあります。
過活動膀胱のよくある症状
- 頻尿
- 夜間頻尿
- 尿意切迫感
- 切迫性尿失禁
過活動膀胱の原因
過活動膀胱の明確な原因は解明されていませんが、膀胱の筋肉や神経の機能異常が関与していると言われています。加齢や膀胱の炎症、神経障害などがリスク要因として知られています。
ストレスと過活動膀胱の関係

過活動膀胱では、頻尿、尿意、切迫性尿失禁といった症状が起こります。膀胱の筋肉や神経の異常に起因するもので、身体的な病態が主要な原因と考えられています。
しかし、精神的なストレスや負担、不安も過活動膀胱の症状悪化に繋がる要因となります。不安やストレスが交感神経の活動を活発化させ、膀胱の収縮を促すことで、過活動膀胱の症状を悪化させる可能性があります。また、過活動膀胱の症状自体が心理的ストレスになる場合もあります。
過活動膀胱の治療では、身体的な治療のほか、リラクゼーションやストレスコントロールなどの精神的な対応も行う場合があります。
過活動膀胱の検査・診断
過活動膀胱の診断は、主に症状に基づいて行われ、特に急激な尿意を催す尿意切迫感が重要な指標となります。また、切迫性尿失禁、頻尿、夜間頻尿も参考となります。具体的には、「過活動膀胱症状質問票」を用いた診断や重症度評価を行います。
質問票を用いたセルフチェックも可能ですが、正確な判断は医師が行います。質問票において、3の質問が2点以上であり、合計点が3点以上の場合は過活動膀胱が疑われます。重症度は合計点に基づいて評価され、5点以下が軽症、11点までが中等症、それ以上が重症と判断されます。
なお、尿意切迫感や頻尿などの過活動膀胱で見られる症状は、膀胱結石、膀胱炎、膀胱腫瘍など、他の疾患でも起こる場合があります。正しい診断のためには、泌尿器科で超音波検査や尿検査などを受け他の疾患との鑑別を行うことが不可欠です。
当院では泌尿器専門医が丁寧な診療を行っております。お気軽にご相談ください。
| 症状 | 回数 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝起きてから夜寝るまでの排尿回数(昼間の排尿回数) | 7回以下 | 0 |
| 8~14回 | 1 | ||
| 15回以上 | 2 | ||
| 2 | 夜寝てから朝起きるまでの排尿回数(夜間の排尿回数) | 0回 | 0 |
| 1回 | 1 | ||
| 2回 | 2 | ||
| 3回以上 | 3 | ||
| 3 | 急激に耐えられないような尿意を感じたことがある(尿意切迫感) | なし | 0 |
| 週1回以下 | 1 | ||
| 週1回以上 | 2 | ||
| 1日1回くらい | 3 | ||
| 1日2~4回くらい | 4 | ||
| 1日5回以上 | 5 | ||
| 4 | 急激に耐えられないような尿意を感じて失禁したことがある(切迫性尿失禁) | なし | 0 |
| 週1回以下 | 1 | ||
| 週1回以上 | 2 | ||
| 1日1回くらい | 3 | ||
| 1日2~4回くらい | 4 | ||
| 1日5回以上 | 5 |
過活動膀胱の治療
生活習慣の見直し

大量の水を飲む、もしくはアルコールやカフェインのような利尿作用があるものを飲むことで尿量が増加し、過活動膀胱の症状が現れる場合があります。このような場合は、水を飲み過ぎないようにする、アルコールやカフェインが含まれる飲み物を控えることで症状が改善することがあります。
また、「トイレに行けないかもしれない」という不安によって症状が起こる場合もあるため、外出前にトイレの場所を把握し、早めに排尿しておくことで心理的な負担を軽くすることも大切です。
膀胱訓練
自宅などトイレにすぐ行ける環境下で、尿意を我慢する訓練を行います。この訓練によって、膀胱の容量を徐々に増やし、症状の改善を目指します。なお、膀胱炎などの尿路感染症を発症しやすい方は、この訓練は行えません。専門医に相談し、ご自身の状態に合わせた適切な方法で膀胱訓練を行うことが大切です。
骨盤底筋体操
骨盤内にある子宮・膀胱・尿道などは、骨盤底筋群という筋肉組織によって支えられ、適切な位置に保持されています。骨盤底筋群が弛緩すると、過活動膀胱の症状が現れやすくなります。骨盤底筋群は筋肉であるため、適切なトレーニングによって強化し、弛緩を改善することが可能です。効果を感じられるようになるまでには一定の時間が必要ですが、根気強く続けることで症状の改善と維持が期待できます。ご自宅で容易に行えるトレーニングですので、日常生活に取り入れ、継続していくことをお勧めします。
薬物療法
膀胱の収縮を抑える効果があるβ3受容体作動薬や抗コリン薬などを使って、症状の改善を目指します。過活動膀胱の治療に用いるお薬は多岐にわたり、効果の発現方法、投与タイミングや方法、副作用などにそれぞれ違いがあります。患者様のライフスタイルや体質を考慮して最適なお薬を選択し、処方を行います。お薬についてご要望やご心配な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
過活動膀胱は治るのか?
若年層の場合
適切な治療を行えば改善が見込めることが多いです。
高齢者の場合
加齢に伴い膀胱の機能が低下するため、比較的治療が難しい傾向にありますが、薬物療法により症状が軽減するケースが多く見られます。
前立腺肥大症を併発している場合
薬物療法や手術などの前立腺肥大症の治療によって前立腺の状態が改善することで、過活動膀胱の症状が軽減する場合があります。
頻尿でお困りの方は当院までご相談ください
尿意をある程度コントロールできる場合は、膀胱訓練によって症状の改善が見込まれます。症状が改善するまでは、薬物療法を併せて行うことで尿意を抑制し、日常生活への影響を小さくすることも可能です。医師の指導の下で行う膀胱訓練は膀胱炎などの尿路感染症のリスクに配慮されており、健康への影響もありませんので、どうぞご安心ください。