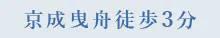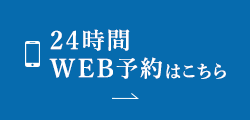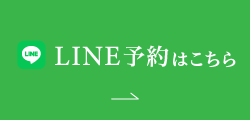口腔アレルギー症候群とは
 口腔アレルギー症候群は、花粉症の患者様が特定の野菜・果物を摂取した際、のど・唇・口などの口腔粘膜やその周りの組織でイガイガ感などのアレルギー症状が生じる状態のことです。食物アレルギーの一種ですが、特異的な特徴を持っています。
口腔アレルギー症候群は、花粉症の患者様が特定の野菜・果物を摂取した際、のど・唇・口などの口腔粘膜やその周りの組織でイガイガ感などのアレルギー症状が生じる状態のことです。食物アレルギーの一種ですが、特異的な特徴を持っています。生野菜や果物を摂取して数分以内に、のど・唇・舌・口でかゆみやむくみ、痺れなどの症状が起こる場合があります。
ほとんどの場合、このような症状が起こっても時間が経てば自然に解消します。しかし、アナフィラキシーショックなどの深刻なアレルギー症状が生じる場合もあるため注意が必要です。
アレルギー症状を招く原因
口腔アレルギー症候群は、生野菜や果物の中のアレルギー原因物質が口内の粘膜と接触することで生じるアレルギー反応です。体内のIgE抗体(アレルギー物質に対する抗体)と関わりがあります。
植物が、傷害や病原体の感染、ストレスから自らを守るために生成するタンパク質がアレルギー原因物質となり、このアレルギー原因物質は小腸に届くまでに破壊されるため、アレルギー反応が生じるのは口内のみの場合が多いです。
花粉症との関係・合併について
花粉症の患者様が果物や生野菜を食べた際、口腔アレルギー症候群が生じることがあります。これは、花粉症の患者様の体内にある花粉のアレルゲンに対するIgE抗体が、果物や生野菜のアレルゲンと構造が類似しているため、誤って反応してしまう「交差反応」が原因となります。
花粉症との合併比率
- スギ花粉症:7〜17%
- イネ科やシラカンバの花粉症:20%
口腔アレルギー症候群の対策
花粉症の患者様で口腔内に症状が現れる場合は、検査で原因となる食物アレルギーを特定し、除去することが必要です。口腔アレルギーを引き起こす生野菜や果物のアレルゲンは加熱によって性質が変化するため、加熱調理することで食べられるようになる場合があります。
症状が頻発する時期には、アレルギー反応を抑えるために抗アレルギー薬を定期的に服用して頂く場合があります。また、症状が現れた際には、速やかに副腎皮質ステロイド薬や抗ヒスタミン薬を使用し、症状の短期的な進行を抑制することが重要です。
軽症の場合はこれらの対応によって1時間以内に症状が改善することが期待できます。しかし、症状が改善しない場合やのどの狭窄感や喘息発作、ショックなどの重篤な症状が現れた場合には、速やかに救急での適切な治療が必要です。
疲れている時は特に注意してください
アレルギー症状はいくつもの誘因が複合することで悪化しやすくなります。口腔アレルギー症候群(OAS)も同様で、風邪・消炎鎮痛薬の使用・疲労・睡眠不足・ストレスなどが複合すると、特に症状が出やすくなります。これらの状態は、自律神経系が失調し、免疫系のバランスも崩れやすくなります。症状が現れた経験がある食物は、体調不良時には避けるよう注意してください。
また、日頃から、疑わしい食物を口にする際は少量から試すようにしましょう。口に少し含み、舌先に少量乗せてみて、違和感やピリピリ感を覚えた場合はすぐに吐き出し、それ以上は食べないようにしましょう。