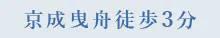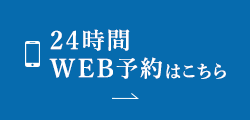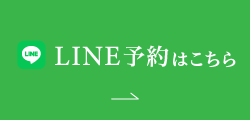女性の泌尿器科
女性は、身体の構造上の問題、月経・妊娠・出産などで排尿障害や膀胱炎などの泌尿器の病気を発症しやすいです。受診に抵抗を感じる方も多いと思いますが、当院では皮膚科の診療にも対応しており、様々な症状で来院される方がいらっしゃいます。安心して受診いただける環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
よくある症状

- 夜間頻尿(夜間に尿意で起きてしまう)
- 頻尿
- 尿漏れ
- 耐えられないほどの激しい尿意で急いでトイレに行く
- 急激な尿意でトイレに間に合わないことがある
- 冷たいものに触る・水音を聞くと、急激な尿意を催す
- 残尿感がある
- 尿の勢いが低下している
- 血尿が出る
- 排尿中や排尿後の痛み
- 健康診断で蛋白尿や尿潜血を指摘された
- 外陰部の不快感や異物感、灼熱感などがある
- 性交痛があるなど
よくある疾患
膀胱炎

膀胱で細菌感染が起こり、炎症が生じる疾患です。急性膀胱炎は排尿の終わり際にツンとするような排尿痛が現れることが多く、残尿感や頻尿、血尿などの症状も現れます。近年は耐性菌が増加しているため、抗生物質の感受性を調べるために培養検査をすることで、患者様の病状に応じた治療を行います。症状が改善したからと自己判断で治療を止めてしまうと、耐性菌が残って完治しづらくなるため、医師の指示に従って最後まで治療を継続しましょう。
また、再発リスクが高いため、十分に水分補給をし、尿意を催したら我慢せずトイレに行くことを意識してください。
骨盤臓器脱
骨盤の中の臓器は骨盤底筋群によって支えられ、正常な場所に収まっています。しかし、出産や加齢によって骨盤底筋群が弛緩すると、臓器の位置が正常な場所から下がる骨盤臓器脱につながる場合があります。膀胱が圧迫されることで、尿漏れや頻尿などの排尿障害が起こりやすく、膣の粘膜越しに下がってきた臓器に触れる場合もあります。骨盤底筋群は適切なトレーニングで鍛えることが出来ますので、保存療法を中心に行い、患者様の状態によって手術療法が検討される場合があります。
過活動膀胱
過活動膀胱は、膀胱内に尿がほとんど溜まっていないにもかかわらず、強い尿意を催す病気です。トイレに着く前に漏らしてしまう場合もあります。発症要因としては、ストレス・加齢・膀胱の知覚過敏・自律神経の失調などが挙げられ、日本では40歳以上の10%程度が発症していると言われています。骨盤底筋群のトレーニングや膀胱訓練、薬物療法を行います。また、十分な水分補給を心掛けましょう。
尿道カルンクル
外尿道口に生じる数mmほどの大きさの良性ポリープです。お尻の近くに発生しやすいですが、自覚症状が少なく、尿が飛び散る・排尿しづらいといった症状をきっかけに見つかる場合があります。また、痛みや頻尿、出血などの症状が現れる場合もあります。
治療ではステロイド軟膏を使用しますが、改善がみられない場合は手術が検討されます。
閉経関連性器尿路症候群(GSM)
閉経に伴いエストロゲン(女性ホルモン)の分泌が減少することで、膣や外陰部、下部尿路が萎縮します。これにより、外陰部の乾燥・かゆみ・灼熱感・におい、急激な尿意・尿漏れ・頻尿・排尿痛、分泌液の減少や性交痛、オルガズム障害など多様な症状をきたし、この状態を閉経関連性性器尿路症候群と言います。病状や症状に応じて潤滑剤や保湿剤などを使ったケア、漢方薬の処方、ホルモン補充療法などによる治療、骨盤底筋群のトレーニングなどを行うことで改善が期待できます。
尿失禁
尿失禁は、切迫性尿失禁(水音などを効くと急激な尿意を催してトイレに間に合わずに漏らしてしまう)、腹圧性尿失禁(くしゃみや咳、ジャンプなどで一時的に腹圧が上昇した際に起こる少量の尿漏れ)、機能性尿失禁(排尿機能に異常はなく、認知や運動機能などの異常によって尿漏れが起こる)、溢流性尿失禁(尿意を感じても正常に排尿できず、少しずつ尿漏れする)などの種類があります。特に切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁が起こりやすいですが、骨盤底筋群のトレーニングや薬物療法によって改善が期待できます。
間質性膀胱炎
膀胱の内側の粘膜の炎症が慢性化し、尿意の亢進・切迫、頻尿、膀胱痛などの症状をきたします。通常の膀胱炎や過活動膀胱でも同様の症状が起こるため、特有のハンナ病変があるか調べるために膀胱鏡検査が行われます。ハンナ病変が見つからない場合、膀胱痛症候群と診断されます。
治療は薬物療法が基本となりますが、紅茶やコーヒー、香辛料、チョコレートなど特定の食品を摂取すると症状が悪化する場合もあるため、生活習慣の改善も大切です。重症の場合は手術を行うこともあります。
腎機能障害
腎機能障害は急性腎障害(AKI)と慢性腎臓病(CKD)に分けられます。腎前性腎不全(腎臓への血流が低下する)、腎性腎不全(お薬の影響や炎症)、腎後性腎不全(尿の流れが滞って排出できなくなる)などが原因として考えられます。
急性腎障害では、全身倦怠感・むくみ・尿量減少などの症状が起こるため、すぐに当院までご相談ください。一方で慢性腎障害は自覚症状が少なく、進行に伴って倦怠感・むくみ・息切れ・尿量減少などの症状が起こります。なお、慢性腎不全でこのような症状が起こる場合、既に病状が進行し、治療が難しいことも多いです。ちょっとした異変を感じたら、すぐに当院までご相談ください。
腎盂腎炎
腎臓で細菌感染が生じ、炎症が起こる疾患です。残尿感や頻尿などの症状が現れ、進行に伴い吐き気・嘔吐、高熱、背中の痛み、尿の濁り、血尿などの症状も現れます。高熱が出ていても咳やのどの痛みなどの症状が見られない場合、腎盂腎炎の疑いが強いため、早急に当院までご相談ください。高齢者や糖尿病の患者様は免疫力が落ちており、重症化して敗血症などが起こると命を落とすリスクもあります。
尿路結石症
腎臓で生成された尿は、尿路(尿管・膀胱・尿道)を通って排出されます。尿路結石症は、尿路に尿中の成分が凝固した結石ができる疾患です。なかでも尿管結石は激しい痛みが起こり、腎盂から送られた結石によって細い尿管が塞がります。尿路結石では、痛みの他にも排尿痛・血尿・頻尿・吐き気・嘔吐などの症状が生じ、急性腎盂腎炎によって発熱症状が現れる場合もあります。レントゲン検査や超音波検査、CT検査などによって結石の大きさやできている場所を調べ、患者様の状態に応じた治療を行います。結石の大きさによっては痛みが生じることなく、長期的に尿管内に留まることで腎機能障害が起こる場合もあるため、早期治療が大切です。
膀胱がん
膀胱がんは環境汚染物質や喫煙が危険因子となると言われており、60代以上の男性に発症しやすいです。発症初期では痛みは現れませんが血尿が出やすく、早期発見できれば負担の少ない内視鏡手術で完治できることもあります。再発を防ぐため、BCGワクチンという上皮がんの治療に効果があるお薬を膀胱内に注入する場合もあります。早期発見が大切な疾患ですので、健康診断の尿検査で尿潜血陽性となった方、もしくは血尿が見られる方はなるべく早めにご相談ください。
腎臓がん
腎臓がんは、高血圧・肥満・喫煙といった生活習慣や、長期透析や遺伝などが危険因子として知られており、50歳以上の男性に多く見られるがんです。初期段階では自覚症状がほとんどなく、進行すると腹部のしこりや血尿などが現れることがあります。近年では、ロボット手術による治療が普及しており、転移が見られる場合でも高度医療機関で適切な治療ができるようになっています。少しでも気になる症状があれば、なるべく早めにご相談ください。
神経因性膀胱
膀胱には蓄尿(尿を蓄積する)と排尿(尿を排出する)の働きがありますが、神経因性膀胱によって蓄尿と排尿を適切に調整できなくなります。尿漏れ・尿意消失・頻尿などがよくある症状で、尿が膀胱の中に長期間留まることで腎機能障害や尿路感染症が起こる恐れもあります。
蓄尿と排尿の働きを調整する末梢神経・脊髄・脳などの異常によって膀胱の機能が低下するため、カテーテルや薬物療法などの治療を行います。しかし、完治が難しいケースも多く、根気強く治療に取り組み、長期的な感染予防で腎機能を温存できるようにすることが大切です。
性感染症
性行為を介して感染する病気を総じて性感染症と言います。クラミジア、淋菌、尖圭コンジローマ、梅毒、性器ヘルペス、毛ジラミ症、HIV感染症などが主な疾患です。昨今、性感染症の患者数が増えており、オーラルセックスによってのどで感染が起こるケースも増えています。女性の場合、性感染症にかかるとおりものが増えたり、においが変化したりすることがありますが、多くの場合は自覚症状がないまま進行します。放置すると、卵管が狭くなり、将来的に不妊症になるリスクもあります。また、妊娠中に感染すると母子感染が起こるリスクもあります。
パートナーが性感染症にかかった場合、ご自身に症状がなくても、感染の有無を調べるために必ず検査を受けましょう。また、ご自身の感染が分かった場合は、パートナーも必ず検査を受けて頂くことが大切です。