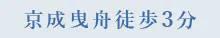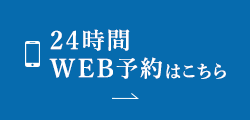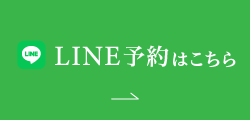尿の色に異変を感じたら注意!膀胱炎の可能性があります!
膀胱炎になると、尿の色が変化することがあります。以下が代表的な変化の例です。
血尿
膀胱炎に伴う炎症や感染によって、尿に血液が混入する場合があります。血尿の場合、基本的には尿が赤色やピンク色になりますが、少量の場合は目視で確認ができないこともありますので、正確な診断には尿検査が必要です。
混濁尿
膀胱炎で尿が濁る場合があります。これは、尿中に細菌や炎症細胞が増加することで、白く濁って見えるためです。
黄色尿
膀胱炎になっても基本的に尿の色は黄色です。これは正常な尿の色と同じですが、その他の症状も含めて総合的な診断が必要です。
膀胱炎について
急性膀胱炎では、陰部から膀胱に細菌が入り炎症を引き起こします。主な症状は、排尿痛や頻尿、残尿感などです。排尿の終わり際にツンとしみるような痛みが起こることが特徴で、炎症の悪化に伴って膀胱粘膜が傷つき、血尿が出る場合もあります。女性は男性よりも尿道が短いため、膀胱に細菌が入り込みやすく、膀胱炎を発症しやすいとされています。水分摂取の不足による尿量の減少、排尿を我慢する習慣は膀胱炎のリスクを高めるため、注意が必要です。
膀胱炎の原因
膀胱に細菌が入り込むことで生じます。原因菌は、大腸などの消化管の中にいる腸内細菌(大腸菌など)であることがほとんどですが、陰部や肛門の周りにも皮膚の常在菌が多数いるため、それらの細菌によって膀胱炎が起こる場合もあります。
また、稀に細菌感染以外の原因で膀胱炎を発症する場合もあります。
膀胱炎の種類
急性膀胱炎
膀胱炎の中で最も頻発するタイプで、大腸菌などの細菌が膀胱内に入り込んで感染が起こり、粘膜に炎症が生じた状態です。特に女性は尿道が短いため発症しやすく、排尿を我慢する習慣や水分摂取の不足による尿量の減少などが発症リスクを高めます。主な症状として、頻尿、残尿感、排尿痛、血尿、白濁尿、下腹部の痛みなどが挙げられ、悪化すると腎盂腎炎を合併して高熱が出るケースもあります。
慢性膀胱炎
膀胱炎が慢性化した状態で、自覚症状がほとんどないか、あっても軽いことがほとんどですが、尿検査では尿の濁りが認められます。膀胱結石、前立腺肥大症、糖尿病など、尿の流れが低下する基礎疾患を持つ方によく見られ、治療が難航することがあります。慢性膀胱炎の場合、背景に潜む疾患を特定し、原因疾患に対する適切な治療を行うことが大切です。
間質性膀胱炎
原因が特定されていない膀胱の炎症で、尿意切迫感や頻尿、膀胱の不快感などの症状が現れます。進行すると、膀胱に尿が溜まるたびに広い範囲で強い痛みが生じ、排尿によって一時的に症状が軽減されることが特徴です。激しい尿意を感じるため、頻繁にトイレに行くようになり、日常生活に大きな支障をきたします。女性に多く見られ、自己免疫疾患やアレルギー反応に関わる肥満細胞による影響が疑われていますが、根本的な原因は解明されていません。コーヒーや香辛料などの刺激物の摂取によって症状が悪化することがあります。ハンナ病変を伴うハンナ型の間質性膀胱炎は、厚生労働省の難病に指定されています。
出血性膀胱炎
主にアデノウイルス感染によって引き起こされ、子どもによく認められます。肉眼ではっきり見ることができる血尿が特徴で、排尿痛・頻尿・残尿感などの激しい症状が現れますが、自然治癒が見込めることが多いです。成人では、お薬の副作用・細菌感染・放射線治療などが原因となります。
放射線性膀胱炎
骨盤内の臓器に対する放射線治療による合併症の1つで、治療後しばらくは自覚症状がないものの、数年後に突然発症することがあります。放射線の影響で新たに形成された血管は非常にもろく、破れやすく出血しやすい状態のため、血尿が生じます。
膀胱炎から腎盂腎炎になるまでの症状
膀胱炎
軽度の膀胱炎
- 頻尿
- 排尿痛
- 尿の濁り
- 激しい尿意・頻尿
中等度の膀胱炎
- 尿が臭い
- 尿の色が濃い
重度の膀胱炎
- 尿意切迫感、排尿痛
- 血尿
- 下腹部痛
腎盂腎炎
軽度の腎盂腎炎
- 膀胱炎の症状だけでなく、背中や腰の側面で軽い痛みが生じる
中等度の腎盂腎炎
- 上記の症状だけでなく、背中や腰の側面の痛みが強くなる
- 発熱
重度の腎盂腎炎
- 上記の症状が強くなり、高熱が長引く
- 腹痛、嘔吐
膀胱炎の治療
急性膀胱炎の治療
急性膀胱炎は細菌感染によって引き起こされることが多いため、抗生物質を用いた治療が効果的です。数日で症状が改善することが多いですが、症状が軽快した後も医師の指示に従ってお薬を飲み続けることが重要です。治療を中断すると症状が再発するだけでなく、抗生物質が効きづらい耐性菌が出現し、治療が困難になる恐れがあります。また、慢性化して腎機能障害が起こりやすくなることもあるため気を付けましょう。
慢性膀胱炎(慢性複雑性膀胱炎)の治療
慢性膀胱炎の治療は急性膀胱炎と同じく抗生物質が用いられますが、別の疾患が潜んでいることがよくあるため、検査によって原因疾患が発見された場合は、その治療も併せて行う必要があります。
間質性膀胱炎の治療
現時点では明確な原因が解明されておらず、根本的な治療法は確立されていませんが、症状を和らげるための対症療法が用いられます。抗アレルギー薬や抗うつ薬が効果を示す場合もあります。また、特定の食品が症状を悪化させることがあるため、原因となる食べ物が判明している場合はできるだけ避けることが推奨されます。さらに、膀胱の機能改善を目的として、膀胱水圧拡張術が行われることもあります。
出血性膀胱炎の治療
アデノウイルスが原因の場合、細菌感染ではないため抗生物質の効果は期待できません。治療の基本は、十分な水分補給と安静です。特に子どもに多く発症し、目に見えるほどの血尿が出ることがあるため驚かれるかもしれませんが、適切な対応をすれば徐々に回復します。通常、数日以内に尿の色が薄れ始め、多くの場合、1週間ほどで回復します。
膀胱炎の予防
膀胱炎は、陰部の周りに付いた腸内細菌が膀胱に入り込むことで起こります。排便時やトイレットペーパーで拭く際に、腸内細菌が陰部の周りの陰毛や皮膚に付き、それが膀胱に侵入することが原因となります。トイレットペーパーで拭く際は前から後ろに拭くなど、日頃の生活習慣を改善することで膀胱炎のリスクを軽減できます。また、尿漏れパッドやナプキンはこまめに交換すること、下痢の際にはシャワーで陰部を洗って清潔に保つことも重要です。なお、ウォシュレットを使用する際は、膀胱への細菌感染を防ぐため、水流が上向きにならないように注意しましょう。
水分補給と膀胱炎の関係

女性は身体の構造上、細菌が膀胱内に侵入しやすいですが、発症初期の軽度な膀胱炎であれば排尿によって細菌が排出され、自然治癒する場合があります。軽い違和感や頻尿が起こっている場合は、十分な水分を摂取してこまめに排尿することで、症状の悪化を防ぐことができます。また、尿意を感じたら我慢せず、早めにトイレに行くようにしましょう。