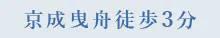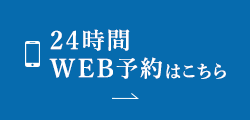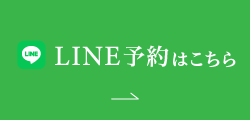子どもの泌尿器科

子どもの泌尿器に関する病気や症状は成長とともに変化するため、適切な時期に適切な治療を行うことが大切です。当院では、夜尿症やお漏らし、水腎症といった男女共通の病気や症状はもちろん、男の子特有の包茎や精巣の異常、性器の形態異常など、様々な病気や症状の治療を行っています。
子どもの泌尿器の症状は、成長に伴って自然に改善する場合もあれば、早期の治療が必要なケースもあります。例えば、1日8回以上もしくは1日3回以下の排尿、昼間の失禁、排尿時の異常(尿の勢いが弱い、途中で途切れる、排尿に時間がかかる、強くいきまないと尿が出ないなど)が見られる場合は、早めの受診をお勧めします。男の子では、性器の見た目に違和感がある、尿の出る場所が通常と違う、陰嚢の中に精巣がない気がするといった場合、何らかの病気の可能性があるため、一度当院までご相談ください。
当院では、お子様と保護者の方に寄り添い、丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけています。不安な症状があれば、遠慮なくご相談ください。
よくある症状
男女いずれでも見られる症状

- 茶色、赤、白濁した尿が出る
- 排尿が1日8回以上
- 排尿が1日3回以下
- 強くいきまないと排尿できない
- 尿の勢いが低下している、時間をかけないと排尿できない
- 排尿の途中で尿が途切れる
- 昼間の失禁
- 夜尿症(おねしょ)など
男の子特有の症状
- 精巣(睾丸)を触ると痛がる
- 急激な精巣(睾丸)の腫れ
- 包皮や亀頭が赤く腫れて痛がっている
- 包茎
- 尿が出る場所が変な気がするなど
よくある疾患
男女いずれでも見られる疾患
排尿障害
排尿痛や頻尿が起こる疾患のほか、夜尿症(おねしょ)や昼間の失禁も該当します。
昼間の失禁
ほとんどの場合、成長に伴って自然と解消されますが、生まれつきの異常が原因となっている場合もありますので、不安な方は一度当院までご相談ください。また、特に異常がない場合でも、昼間の失禁がなかなか治らないことで尿路感染症や腎機能障害が起こりやすくなります。病気の予防と早期発見のために、お悩みの方は遠慮なくご相談ください。
夜尿症(おねしょ)
夜尿症は、5歳以上の子どもが、3ヶ月以上にわたり月に1回以上おねしょをする状態です。なお、おねしょをしなくなる時期は人によって異なり、4~5歳では70~80%の子どもに見られ、小学校入学時でも10~15%の子どもに見られると言われています。夜尿症の原因は、夜間に生成される尿量と膀胱に溜められる尿量のバランスが取れないこと、膀胱の発達が未熟であること、夜間の水分摂取量が多いことなど、多様な要因が複雑に関係しています。そのため、夜尿症の原因に応じて薬物療法・行動療法・生活指導などを組み合わせ、根気強く治療を行っていきます。
膀胱尿管逆流症
膀胱尿管逆流症は、膀胱に溜まった尿が尿管や腎臓に逆流する疾患です。尿路感染症を発症しやすく、腎盂腎炎や水腎症を引き起こし、腎臓機能の低下や慢性腎不全に至るリスクがあります。脇腹や背中の痛み・排尿痛・頻尿・吐き気・嘔吐・高熱などの症状が現れた場合は、尿路感染症の可能性があるため、なるべく早めに当院までご相談ください。
神経因性膀胱
神経因性膀胱は、脳、脊髄、末梢神経などの神経系の異常で、膀胱の運動機能や知覚機能が低下し、頻尿・尿漏れ・排尿困難などが起こる病気です。尿が膀胱内に長時間残ることで、腎機能障害や尿路感染症が起こりやすくなります。感染症を防ぎ、腎臓の機能を維持するために、病状に応じた治療を継続することが大切です。
水腎症
水腎症は、尿の排出に支障をきたし腎盂が腫れる疾患です。20~50人に1人の確率で発症すると言われており、特に胎児期に発症しやすく、妊娠中の超音波検査で見つかるケースが増えています。自然治癒する場合もありますが、手術を要する場合もあります。そのため、定期的な経過観察が重要です。また、成長してから腰痛や腹痛などの症状が現れ、受診した際に水腎症が見つかる場合もあります。
男の子特有の疾患
包茎
包茎には、包皮を全く剥くことができない真性包茎、亀頭を露出できるが普段は包皮に覆われている仮性包茎、剥いた包皮が亀頭の根元を強く圧迫し、元に戻せなくなった状態の嵌頓包茎があります。嵌頓包茎は血流が阻害され、放置すると壊死のリスクがあるため、すぐに適切な処置を受ける必要があります。
真性包茎
包茎は、包皮を剥いて亀頭を露出させることができない状態です。生まれたばかりの赤ちゃんは全員が包茎で、無理に包皮を剥こうとすると、嵌頓包茎という危険な状態になる恐れがあります。子どもの包茎について不安なことがあれば、当院までご相談ください。子どもの包茎は成長に伴って自然に改善することが多いですが、包皮炎が頻発するなどの症状が見られる場合は、手術を行う場合もあります。
また、成長してからも真性包茎が改善しない場合は、陰茎がんのリスクや性行為への影響が懸念されるため、手術を推奨しております。
仮性包茎
仮性包茎は、包皮を手で剥けば亀頭を露出できる状態です。しかし、仮性包茎であっても、剥いた包皮が元に戻らなくなる嵌頓包茎を引き起こす可能性があります。嵌頓包茎は血流が阻害される危険な状態ですので、もし包皮が戻らなくなってしまった場合は、速やかに当院までご相談ください。仮性包茎の場合、基本的に治療は不要です。しかし、包皮炎が頻発する場合は手術を行うことがあります。
嵌頓包茎
嵌頓包茎は、包皮を剥いた際に包皮輪が亀頭を強く圧迫し、元の状態に戻せなくなってしまった状態です。血流が阻害されることで亀頭が腫れ上がり、強い痛みを伴います。放置すると、組織が壊死してしまう危険性があるため、早急な処置が必要です。
亀頭包皮炎
亀頭包皮炎は、亀頭や包皮に細菌や真菌が繁殖し、炎症を引き起こす疾患です。他者にうつることはありませんが、腫れ・赤み・膿・ただれなどの症状が現れ、激しいかゆみや痛みが起こる場合もあります。包茎の方は、亀頭や包皮を清潔に保ちにくいため、亀頭包皮炎が頻発する場合があります。
陰嚢水腫
陰嚢水腫は、陰嚢内で精巣の周りに液体が溜まり、陰嚢が腫れる疾患で、新生児によく見られます。胎児期では精巣は腹部に存在しますが、生まれる前に腹膜と一緒に陰嚢へ移動し、その後腹膜が閉じます。腹膜が閉じないと、腹部の水分が陰嚢に流出し、陰嚢水腫が起こります。
移動性精巣
移動性精巣(別名:迷走睾丸)は、陰嚢に触れた際に精巣の存在が分かる時と分からない時がある状態です。思春期前に筋肉の収縮によって精巣が鼠径部へ上がることがあり、その際に陰嚢に触れても精巣が感じられないことがあります。入浴時など筋肉が緩んでいる状態で陰嚢を触れ、左右で大きさに違いがなければ、移動性精巣である可能性があります。
一方、停留精巣の場合、筋肉の緊張が解けた状態でも精巣が感じられません。子どもの精巣は非常に小さく、移動性精巣でも触診では確認しにくいことがあります。当院では、熟練の医師が超音波検査を用いて精巣の位置を正確に確認しておりますので、心配なことがあればどうぞお気軽にご相談ください。
停留精巣
停留精巣は、精巣が腹部から陰嚢まで降りてきていない状態で、男の子の先天性の病気の中で最も多いです。生まれたばかりの男の子の約3%に見られます。精巣は精子を生成する上で体温よりも低い環境を必要とするため、腹部から陰嚢へ移動します。精巣が降りてくる時期は人によって異なりますが、生後1年以内に自然に降りてくることがほとんどです。なお、1歳を過ぎても約1%の男の子は停留精巣の状態が続くことがあります。停留精巣を放置すると、将来的に不妊に繋がる恐れがあります。しかし、手術によって停留精巣を治療することができますので、子どもの精巣について心配なことがあれば、なるべく早めに当院までご相談ください。
尿道下裂
基本的に尿道の出口は亀頭の先端に位置しますが、場合によっては陰嚢、陰茎の根元、亀頭部のくびれなど、通常とは異なる場所に開口することがあります。尿の出口の位置に関して心配な点や分からないことがあれば、なるべく早めに当院までご相談ください。
精巣捻転
精巣捻転は、精巣が回転し、酸素や栄養素を供給する血管が捻れてしまう状態です。これにより、下腹部や陰嚢で強い痛みが生じます。新生児にも起こる場合がありますが、10代以降に起こるケースも多いです。血流が阻害されると精巣が壊死してしまう恐れがあるため、下腹部や陰嚢に激しい痛みを感じた場合は、血流を調べるためすぐに超音波検査を受ける必要があります。血流障害が確認された場合は、緊急手術を行います。陰嚢の強い痛みは、精巣上体炎など別の疾患でも現れることがありますので、正しい診断が大切です。