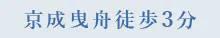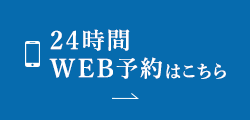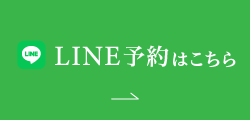亀頭包皮炎とは
 亀頭包皮炎は、男性の性器の先端部の亀頭と、それを覆う皮膚の包皮に炎症が生じる病気です。腫れ、発赤、膿、かゆみなどの症状を示し、特に皮膚が敏感な方や包茎(仮性包茎・真性包茎)の方、糖尿病の患者様が発症しやすいと言われています。
亀頭包皮炎は、男性の性器の先端部の亀頭と、それを覆う皮膚の包皮に炎症が生じる病気です。腫れ、発赤、膿、かゆみなどの症状を示し、特に皮膚が敏感な方や包茎(仮性包茎・真性包茎)の方、糖尿病の患者様が発症しやすいと言われています。
包皮や亀頭の温度や湿度などが真菌や細菌の増加に適した環境となり、カビの一種である真菌感染や、常在菌の異常増殖に繋がる場合があります。また、性感染症であるクラミジアや淋菌による感染が原因で起こるとも言われています。さらに、石鹸による過剰な洗浄や強い刺激が原因で炎症が生じる場合もあり、様々な原因が複合的に関与していることもあります。放置すると症状が悪化する恐れがあるため、疑わしい症状が現れた場合はなるべく早めにご相談ください。
亀頭包皮炎の原因
包皮や亀頭は垢が蓄積しやすく、真菌や細菌が増加しやすい温度・湿度であるため、常在菌である黄色ブドウ球菌、大腸菌、真菌などの感染によって炎症が生じやすいです。衛生状態が悪いと感染しやすくなりますが、過剰な洗浄により皮膚の防御機能が低下し、感染リスクが高まることもあります。
性感染症であるクラミジアや淋菌の感染によって亀頭包皮炎の症状が現れる場合があり、一般細菌との混合感染も考えられます。
また、強い洗浄力を持つ石鹸や過度な洗浄による摩擦、アレルギーなど、感染症以外の原因で亀頭包皮炎が起こる場合もあります。
亀頭包皮炎の症状
炎症が生じているため、腫れや発赤、熱感などが現れます。痛みやかゆみを伴うことも多く、皮膚の剥離や膿の排出などの症状が見られる場合もあります。
原因菌によって症状の特徴が異なり、その特徴を手がかりに感染源を特定するための検査を行うことができます。例えば、一般的な細菌感染症や淋菌感染症では、顕著な発赤が見られることが多く、黄色の膿や腫れなども見られます。真菌の一種であるカンジダ感染症では、黄色または白色の悪臭を伴うカスが蓄積し、激しいかゆみが起こりやすくなります。これらの症状を注意深く観察し、適切な検査を実施することで、正確な診断につなげています。
亀頭包皮炎のリスクが高い方
 包茎の場合、亀頭が常に包皮で覆われているため、清潔な状態を維持することが難しく、真菌や細菌が増加しやすい湿度・温度になるため、常在菌による亀頭包皮炎のリスクが高まります。
包茎の場合、亀頭が常に包皮で覆われているため、清潔な状態を維持することが難しく、真菌や細菌が増加しやすい湿度・温度になるため、常在菌による亀頭包皮炎のリスクが高まります。
また、睡眠不足や疲労、運動不足、偏った食生活、不規則な生活習慣、精神的ストレスなどにより免疫力が落ちていると感染しやすくなり、亀頭包皮炎が頻発する場合があります。糖尿病を患っており尿糖が出ている方や、糖尿病の治療薬として尿中に糖を排出するお薬を服用している方も発症しやすく、免疫抑制療法を受けている方も感染しやすいとされています。
皮膚の乾燥や過度な洗浄により保護機能が低下していると、感染リスクが高まります。アトピー性皮膚炎の方は、炎症部位から細菌が侵入する場合もあります。
亀頭包皮炎の検査・診断
問診で詳細な症状を確認し、必要があれば視診で状態を観察します。細菌性の亀頭包皮炎の可能性があれば、粘膜や皮膚の病変から組織を採取し、培養検査を行うことで、原因菌を突き止めます。
亀頭包皮炎の治療
細菌性の亀頭包皮炎の場合、抗生物質の内服薬や外用薬を用いた治療が効果的です。一方、真菌の一種であるカンジダの感染によって起こっている場合は、抗生物質を使った治療では効果が乏しく、抗真菌薬による治療を行います。
なお、複数の病原体に同時感染している場合や、真菌と細菌の混合感染が生じている場合もあります。そのような場合は、複数のお薬を組み合わせた治療が効果的です。
また、真菌や細菌などの病原体感染が原因ではない亀頭包皮炎に対しては、炎症を抑える外用薬を用いた治療を実施します。
市販薬と処方薬の違い
亀頭包皮炎は、かゆみや赤みといった日頃からよく見られる症状が生じやすいため、ご自身の判断で市販薬を使用する方がいらっしゃいます。しかし、原因となる病原体によっては、市販薬では症状の改善が見込めず、医療機関で処方されるお薬でなければ治療できない場合も多いです。また、患部はデリケートゾーンであり、炎症によって敏感になっているため、市販薬の刺激によって症状が悪化する恐れもあります。早期に有効な治療を行うためには、医療機関での検査と適切な処置が不可欠です。お悩みの症状があれば、遠慮なくご相談ください。
亀頭包皮炎で気を付けること
 不十分な衛生管理によって発症しやすくなりますが、清潔を維持しようと洗い過ぎることも皮膚の保護機能を弱め、感染の原因になり得ます。また、強い洗浄力があるボディーソープや石鹸を使用する、力を入れてこすり洗いするなどの刺激によって炎症を誘発することがあります。治療中は当然ですが、治癒後もぬるま湯で優しく洗い流すことを意識してください。
不十分な衛生管理によって発症しやすくなりますが、清潔を維持しようと洗い過ぎることも皮膚の保護機能を弱め、感染の原因になり得ます。また、強い洗浄力があるボディーソープや石鹸を使用する、力を入れてこすり洗いするなどの刺激によって炎症を誘発することがあります。治療中は当然ですが、治癒後もぬるま湯で優しく洗い流すことを意識してください。
また、クラミジア、淋菌、カンジダなどの性感染症に罹患している場合、パートナーも感染している恐れがあるため、必ず検査を受けるよう促してください。性感染症は、症状が落ち着いても病原体が体内に潜伏している間は完治したことになりません。治療後に再度検査を受け、病原体の消滅を確かめることが大切です。